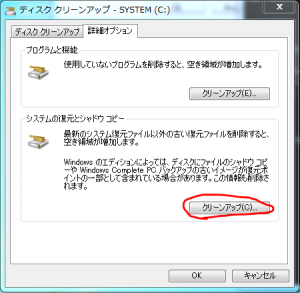食生活
日本人の食事内容のうち、摂取カロリーに占める割合が1960年度と比べて大幅に減ったものは?
[B] - 米
暑い夏などに、糖分を含む飲料水を飲み過ぎることによって体調を崩してしまうのは何症候群?
[B] - ペットボトル症候群
食べたものからカルシウムを効率よく吸収するために、あわせてとるとよいのがビタミンD。では、ビタミンDを効率的に摂取できる食品は?
[A] - サケ
減塩しても料理が味気なくなってしまわないようにするために、利用するとよいのは?
[A] - うまみ
飲酒と尿酸の関係について間違っているのは?
[C] - プリン体を含まない酒類なら飲んでも尿酸値は上がらない
身体活動と運動
骨や筋肉、神経などの障害によって、移動機能が低下することを何という?
[B] - ロコモティブシンドローム
標準体重(60kg)の人が10分間歩いたときに消費するエネルギーは?
[A] - 約30kcal
国民の身体活動量を増やすために厚生労働省が推奨する「+10(プラステン)」とは?
[A] - 1日10分間多く体を動かす
筋肉や関節を伸ばすストレッチをじっくり静的に行うことで優位になる神経は?
[C] - 副交感神経
次のうち、血糖の調節に最も直接的に関わっているのは?
[A] - 筋肉
睡眠とメンタルヘルス
寝付きのよくなる入浴法として間違っているのは?
[C] - 湯舟に入る時間がとれない日は、シャワーを含む入浴自体を控えた方が良い
睡眠を妨げる睡眠時無呼吸症候群。そのサインではないものは?
[C] - 食欲低下
相手を傷つけずに自己主張する「アサーション」。例えば、忙しいときに上司から別の仕事を頼まれた場合、どう答えたらよい?
[A] - 今日は今の仕事で手いっぱいなので、明日でもいいですか?
ストレスを感じたとき、緊張をゆるめるために行う筋弛緩法について正しいのは次のどれか?
[B] - 緊張だけでなく不安にも効果的
自分の偏ったものの見方に気づいて、ふだんとは違う捉え方を探るトレーニングを何というか?
[C] - 認知行動療法
がん
子宮体がんと乳がんの発生に大きく影響するホルモンの名前は?
[A] - エストロゲン
がんの原因にもなるピロリ菌は体のどこに生息する?
[C] - 胃
人間ドックなどで、肺がん検診のために胸部X線検査とともに行われるのは?
[C] - 喀痰(かくたん)細胞診
がん検診の便潜血検査で「要精密検査」となった場合、次にどの検査を受けられる医療機関を受診する?
[A] - 大腸内視鏡検査
がん検診でがんが疑われて精密検査をしても、結局がんは無かったと診断された場合、がん検診の所見は「〇〇〇」であったといえる。
[A] - 偽陽性
オーラルケア
歯周病のサインは?
[A] - 歯と歯の間にものが挟まる
歯磨きのポイント、間違っているのは?
[B] - しっかり力を入れて磨く
歯を失う原因として最も多いのは?
[B] - 歯周病
歯の再石灰化についての説明で間違っているのは?
[C] - 再石灰化は、唾液に溶けている酵素が補充されることである
歯周病と糖尿病の関係で間違っているのは?
[A] - 糖尿病の人が一度歯周病になると、歯周病を治療しても糖尿病は改善しない
トレンド
ジェネリック医薬品とは、どんな医薬品?
[B] - 先発医薬品の特許が切れた後に、別のメーカーから販売される後発医薬品
熱中症対策として、全身を効果的に冷やすことができる部位は?
[A] - 脇の下
「脳ドック」の検査で早期発見できる病気は次のうちどれ?
[C] - くも膜下出血
人間ドックなどで行う眼底検査によって異常がわかるのは、どの病気?
[B] - 糖尿病網膜症
介護保険法に基づく公的な介護保険の保険料徴収が始まるのは何歳から?
[C] - 40歳